前回は「変数」「計算」「文字列」について学びました。
今回はプログラムに「もし〜なら」という考え方を入れてみましょう。
この仕組みを 条件分岐(if文) といいます。
1. if文の基本形
Pythonのif文はとてもシンプルです。
x = 10
if x > 5:
print("xは5より大きい")
実行すると、
xは5より大きいと表示されます。
ポイントは インデント(スペースでの字下げ) です。
Pythonでは「条件が成立したときに実行する処理」を 字下げ で表します。
2. elseを使ってみよう
「そうでなければ」という処理も書けます。
x = 3
if x > 5:
print("xは5より大きい")
else:
print("xは5以下です")結果は
xは5以下ですとなります。
3. 複数の条件(elif)
「もしこれなら…」「そうじゃなくて、もしあれなら…」と条件を増やすときは elif を使います。
score = 75
if score >= 80:
print("合格!よくできました")
elif score >= 60:
print("合格!")
else:
print("残念、不合格です")4. 実際に遊んでみよう
ちょっとした「数当てゲーム」を作ってみましょう。
number = 7
guess = int(input("数字を入力してください: "))
if guess == number:
print("正解!")
elif guess > number:
print("大きすぎます")
else:
print("小さすぎます")Colabで実行すると、自分で数字を入力して遊べます。
まとめ
- if文で「もし〜なら」を表現できる
- elseで「そうでなければ」を追加できる
- elifで条件を増やせる
- 入力を組み合わせると簡単なゲームも作れる
これで「考えるプログラム」が作れるようになりました!
次回は 「繰り返し(for文・while文)」 を学んで、同じ処理を自動で何回も実行してみましょう。
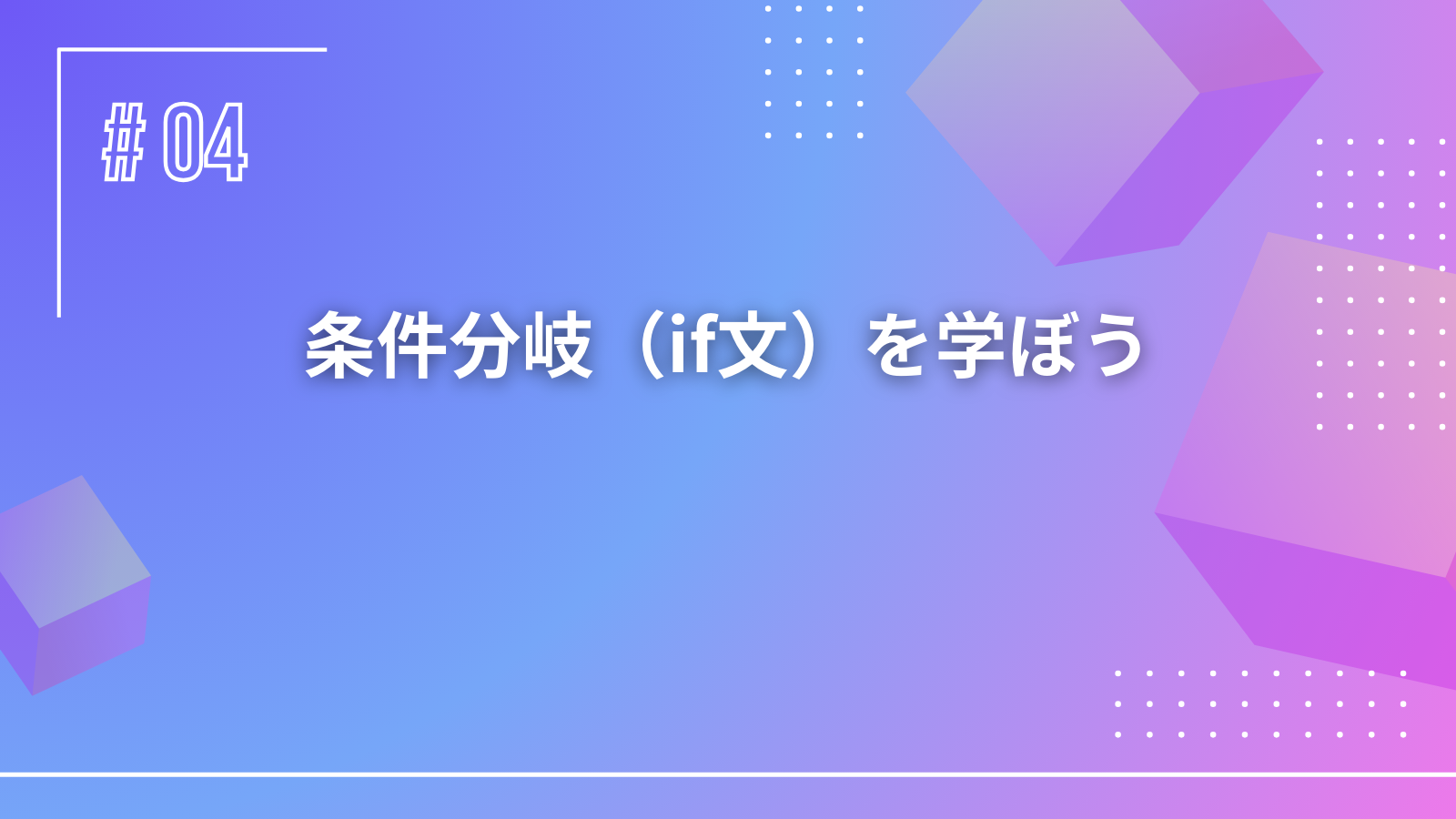
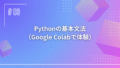
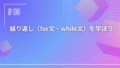
コメント