こんにちは、KENEKNです。
前回の記事では、私がなぜ統計検定2級を受けようと思ったのかについて書きました。今回は、実際に統計検定2級ではどんな内容が出題されるのかをご紹介します。
統計検定2級の概要
統計検定は、日本統計学会が実施している資格試験で、統計に関する知識を体系的に学び、証明できるものです。
その中でも2級は「高校~大学初年度程度の統計学」が出題範囲になっています。試験形式はマークシート式で、制限時間は60分。実際の業務やデータ分析に必要となる基礎的な力が問われます。
出題範囲
統計検定2級では、以下のようなテーマが中心です。
- データの整理・記述統計
平均、分散、標準偏差、ヒストグラム、箱ひげ図など、データをまとめて特徴を把握する方法。 - 確率と確率分布
サイコロやコインのような基本的な確率から始まり、二項分布・ポアソン分布・正規分布など、統計でよく使われる確率分布。 - 推定と検定
母集団の平均や割合を区間推定したり、仮説検定(t検定、χ²検定など)を行ってデータの違いを判断する方法。 - 相関と回帰
変数同士の関係性を調べる相関係数や、予測に使う回帰分析の基礎。 - その他のトピック
分散分析や母集団と標本の考え方など、統計的な思考に必要な要素。
難易度と合格率
合格率はおおよそ30〜40%前後(年度によって変動あり)。
基礎をしっかり理解していないと計算問題でつまずきやすいため、テキストや過去問を繰り返して「なぜそうなるのか」を意識することが大切です。
勉強のポイント
- 数式を丸暗記するのではなく、考え方を理解する
- 過去問でよく出るテーマを重点的に対策する
- 手を動かして計算を解きながら学ぶ
まとめ
統計検定2級は「データサイエンスの入口」にぴったりの試験です。AIや機械学習を理解するための土台作りにもなるので、これからの学びに役立つと感じています。
次回は、私が立てた勉強計画と使用する教材について紹介します。
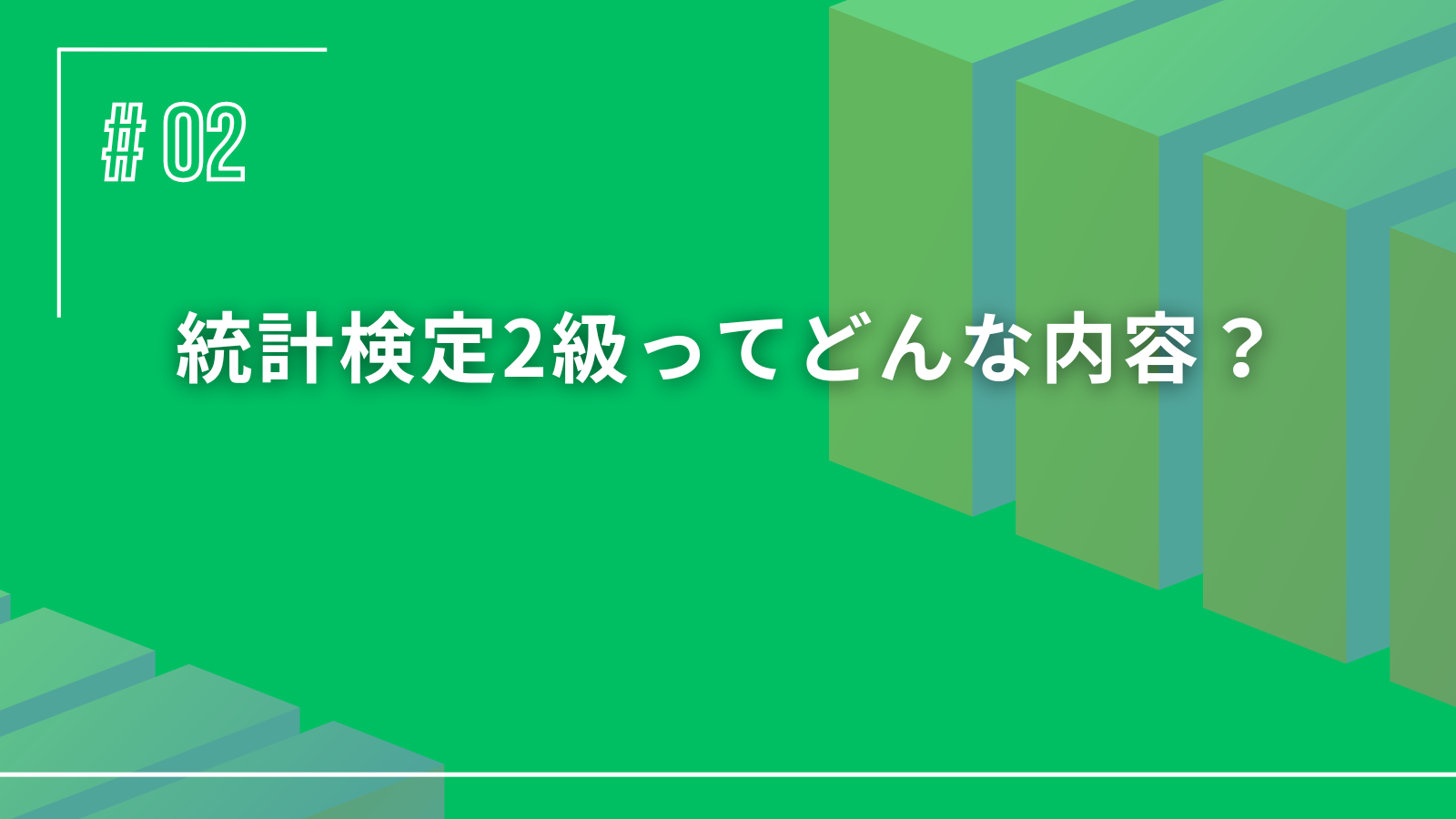
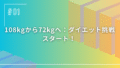
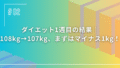
コメント